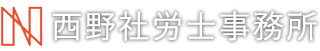労働者の給与と企業の経済状態のバランスを取ることは、経営者や人事担当者の重要な役割の一つです。特に欠勤控除に関しては、従業員の給与やモチベーション、企業の生産性と直結しているため、適切な取り扱いが求められます。しかし、どのようにして欠勤控除を公平かつ適切に実施するのか、多くの企業が悩むポイントです。この記事では、欠勤控除の基礎知識から具体的な計算のコツまでを解説し、より公平で効果的な欠勤控除の方法を提案します。

欠勤控除の根幹:理念とその意義

欠勤控除は、給与制度の公平性を維持するための重要な制度であり、その背後には「ノーワーク・ノーペイ」の理念が存在します。
給与は、従業員が提供する労働に対する対価として支払われるものです。従って、提供される労働が減少する場合、その対価も減少するのが公平であると考えられます。「ノーワーク・ノーペイ」の理念は、労働に対する対価という考え方を明確にしたもので、この理念は欠勤控除の基盤となっています。
たとえば、AさんとBさんが同じ仕事内容、同じ給与で働いているとします。Aさんが1日欠勤し、そのまま全額の給与を受け取った場合、Bさんとの給与の公平性が保たれません。このケースで欠勤控除を行うことにより、労働した時間に応じた給与が支払われることとなり、公平性が維持されます。
従って、欠勤控除は単なる給与の減額ではなく、労働と給与の公平性を守るための制度であると言えます。この制度を適切に運用することで、企業内の給与の公平性と従業員のモチベーションの維持が期待できます。
給与は、従業員が提供する労働に対する対価として支払われるものです。従って、提供される労働が減少する場合、その対価も減少するのが公平であると考えられます。「ノーワーク・ノーペイ」の理念は、労働に対する対価という考え方を明確にしたもので、この理念は欠勤控除の基盤となっています。
たとえば、AさんとBさんが同じ仕事内容、同じ給与で働いているとします。Aさんが1日欠勤し、そのまま全額の給与を受け取った場合、Bさんとの給与の公平性が保たれません。このケースで欠勤控除を行うことにより、労働した時間に応じた給与が支払われることとなり、公平性が維持されます。
従って、欠勤控除は単なる給与の減額ではなく、労働と給与の公平性を守るための制度であると言えます。この制度を適切に運用することで、企業内の給与の公平性と従業員のモチベーションの維持が期待できます。
欠勤とその影響: 基本的な定義
欠勤は、従業員が予定された勤務時間中に職場に出席しないことを指します。これは様々な理由、例えば病気や家庭の事情、個人的な理由によるものまで幅広く存在します。欠勤には、事前に知らせる場合と突発的に出てくる場合があり、それぞれの企業や組織が独自の対応を取ることが一般的です。
欠勤の影響は多岐にわたります。一番明確な影響は業務の遂行です。欠勤が発生すると、その人の分の業務が滞る可能性があるため、他のメンバーがその業務を引き継ぐことが求められることが多いです。また、組織全体の生産性や効率性にも影響を及ぼすことが考えられます。
このように、欠勤は個人の事由から発生するものですが、その影響は組織全体に及ぶことが多いのです。したがって、欠勤の管理や対応は、人事労務の視点からも非常に重要なテーマと言えるでしょう。
欠勤の影響は多岐にわたります。一番明確な影響は業務の遂行です。欠勤が発生すると、その人の分の業務が滞る可能性があるため、他のメンバーがその業務を引き継ぐことが求められることが多いです。また、組織全体の生産性や効率性にも影響を及ぼすことが考えられます。
このように、欠勤は個人の事由から発生するものですが、その影響は組織全体に及ぶことが多いのです。したがって、欠勤の管理や対応は、人事労務の視点からも非常に重要なテーマと言えるでしょう。
「ノーワーク・ノーペイ」の理念の深層
「ノーワーク・ノーペイ」は、公平性と報酬の正当性を保つための基本的な考え方です。
この理念は、労働と報酬のバランスを重視するもので、働いた分だけ報酬を得るという原則に基づいています。従業員と雇用者の間の信頼関係を築くために、労働の成果と報酬の間に透明性と公平性を保つことが重要であり、この原則はその考え方を具現化したものと言えます。
例えば、Aさんが月に20日勤務する契約で働いている場合で5日欠勤したとします。この場合、Aさんの報酬は、実際に働いた15日分のみとなります。これにより、他の従業員との公平性が保たれ、労働意欲やモチベーションの維持も促されます。
このように、「ノーワーク・ノーペイ」の理念は、公平で透明な労働環境を構築するための基石であり、組織の健全な運営には欠かせない考え方といえます。
この理念は、労働と報酬のバランスを重視するもので、働いた分だけ報酬を得るという原則に基づいています。従業員と雇用者の間の信頼関係を築くために、労働の成果と報酬の間に透明性と公平性を保つことが重要であり、この原則はその考え方を具現化したものと言えます。
例えば、Aさんが月に20日勤務する契約で働いている場合で5日欠勤したとします。この場合、Aさんの報酬は、実際に働いた15日分のみとなります。これにより、他の従業員との公平性が保たれ、労働意欲やモチベーションの維持も促されます。
このように、「ノーワーク・ノーペイ」の理念は、公平で透明な労働環境を構築するための基石であり、組織の健全な運営には欠かせない考え方といえます。
欠勤控除の計算:基礎と詳細
欠勤控除の計算は、労働者の公平な報酬を確保するための重要な手段であり、それを適切に行うためには基礎から詳細までの知識が必要です。
労働者が提供する労働の価値と、その対価として受け取る報酬は直接的な関係があります。欠勤控除は、働かなかった時間や日数に対する報酬を減額する制度で、これによって労働と報酬のバランスが維持されます。
たとえば、月給20万円の労働者が1か月のうち5日間欠勤した場合、月の所定労働日数を20日とすると、1日あたりの給与は10,000円となります。従って、5日間の欠勤による控除額は50,000円となります。このように、具体的な計算を行うことで、欠勤に対する報酬の減額を公平に行うことができます。
欠勤控除の計算は、労働者と企業双方にとって公平性を保ちつつ、適正な報酬を確保するための基本的な手段です。その適切な適用のためには、計算の基礎から詳細にわたる知識の習得が不可欠です。
労働者が提供する労働の価値と、その対価として受け取る報酬は直接的な関係があります。欠勤控除は、働かなかった時間や日数に対する報酬を減額する制度で、これによって労働と報酬のバランスが維持されます。
たとえば、月給20万円の労働者が1か月のうち5日間欠勤した場合、月の所定労働日数を20日とすると、1日あたりの給与は10,000円となります。従って、5日間の欠勤による控除額は50,000円となります。このように、具体的な計算を行うことで、欠勤に対する報酬の減額を公平に行うことができます。
欠勤控除の計算は、労働者と企業双方にとって公平性を保ちつつ、適正な報酬を確保するための基本的な手段です。その適切な適用のためには、計算の基礎から詳細にわたる知識の習得が不可欠です。
休日と休暇:二つのキーポイントの違い

休日と休暇は、働く者にとって重要な概念であり、欠勤控除の計算においてもその違いを正確に理解することが不可欠です。
欠勤控除の計算を行う際、休日と休暇は異なる取り扱いが必要です。労働者の権利としての休息の日(労働義務が無い日)と、特定の理由での欠勤が認められる日(労働義務を免除する日)は、労働法的な背景に基づいた異なる意義を持つため、この二つの概念を混同することは誤った控除の原因となる可能性があります。
例として、Aさんは週5日のフルタイムで働いています。土日が休日の場合、これらの日には基本給がそのまま支払われます。一方、Aさんが平日に有給休暇を取得した場合、この日も給与はそのまま支払われるが、これは「休暇」としての権利に基づくものです。また、無給の休暇を取得した場合、その日の給与が控除される場合があります。休日と休暇の違いを正確に理解しないと、欠勤控除の計算で誤りが生じるリスクが高まります。
一方、休日はもともと労働義務が無いので、休日に休んでも当然のこととして、給料の計算には影響しません。
休日と休暇の違いを明確に理解することは、欠勤控除の正確な計算のための基本中の基本です。正確な知識を持つことで、労働者の権利を尊重しつつ、公平な給与計算を行うことが可能となります。
【休日と休暇の違いについては、こちらで詳しく解説しています】
欠勤控除の計算を行う際、休日と休暇は異なる取り扱いが必要です。労働者の権利としての休息の日(労働義務が無い日)と、特定の理由での欠勤が認められる日(労働義務を免除する日)は、労働法的な背景に基づいた異なる意義を持つため、この二つの概念を混同することは誤った控除の原因となる可能性があります。
例として、Aさんは週5日のフルタイムで働いています。土日が休日の場合、これらの日には基本給がそのまま支払われます。一方、Aさんが平日に有給休暇を取得した場合、この日も給与はそのまま支払われるが、これは「休暇」としての権利に基づくものです。また、無給の休暇を取得した場合、その日の給与が控除される場合があります。休日と休暇の違いを正確に理解しないと、欠勤控除の計算で誤りが生じるリスクが高まります。
一方、休日はもともと労働義務が無いので、休日に休んでも当然のこととして、給料の計算には影響しません。
休日と休暇の違いを明確に理解することは、欠勤控除の正確な計算のための基本中の基本です。正確な知識を持つことで、労働者の権利を尊重しつつ、公平な給与計算を行うことが可能となります。
【休日と休暇の違いについては、こちらで詳しく解説しています】
欠勤控除:基本給以外の諸手当の取扱い
先ほどこのような例をあげました。
-------------------------------------
月給20万円の労働者が1か月のうち5日間欠勤した場合、月の所定労働日数を20日とすると、1日あたりの給与は10,000円となります。
------------------------------------
ところが、いざ計算しようとした時に、様々な疑問が生じます。
・基本給だけなら問題無いのですが、諸手当はどうするのか?
・月の所定労働日数は、20日の月や19日の月、21日の月など、その月によって変動します。その場合、1日あたりの欠勤控除額が変動するのでは?
残業代の計算については、労働基準法で定められているのですが、欠勤控除に関する規定はありません。各社の就業規則で規定することになります。ここでは、欠勤控除をするための具体的な考え方を解説します。
【残業代の計算については、こちらで詳しく解説しています】
-------------------------------------
月給20万円の労働者が1か月のうち5日間欠勤した場合、月の所定労働日数を20日とすると、1日あたりの給与は10,000円となります。
------------------------------------
ところが、いざ計算しようとした時に、様々な疑問が生じます。
・基本給だけなら問題無いのですが、諸手当はどうするのか?
・月の所定労働日数は、20日の月や19日の月、21日の月など、その月によって変動します。その場合、1日あたりの欠勤控除額が変動するのでは?
残業代の計算については、労働基準法で定められているのですが、欠勤控除に関する規定はありません。各社の就業規則で規定することになります。ここでは、欠勤控除をするための具体的な考え方を解説します。
【残業代の計算については、こちらで詳しく解説しています】
基本給以外の諸手当:欠勤控除できる手当とできない手当
残業代の計算に当たっては、労働基準法でベースになる給料から除外できるものは、下記に限定されています。
①1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナス等)
②通勤手当
③家族手当
④住宅手当
⑤別居手当
⑥子女教育手当
⑦臨時に支払われた賃金
逆に言うと、上記の手当以外は全て残業代のベースに含まれることになります。
なお、固定残業代(みなし残業代)は、あくまで残業代であるため、残業代のベースからは除外するのが一般的な考え方です。
欠勤控除については、労働基準法での定めがないため、会社で独自に定め、就業規則に規定します。
残業代のルールをそのまま適用するのも1つの考え方ですが、それにとらわれる必要はありません。仮にその月の全てを欠勤した時、残業代のルールを適用した場合、上記の手当や固定残業代(みなし残業代)は支給されます。
各手当の性質をもとに、会社としての考え方を基準に具体的に定めてください。
①1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナス等)
②通勤手当
③家族手当
④住宅手当
⑤別居手当
⑥子女教育手当
⑦臨時に支払われた賃金
逆に言うと、上記の手当以外は全て残業代のベースに含まれることになります。
なお、固定残業代(みなし残業代)は、あくまで残業代であるため、残業代のベースからは除外するのが一般的な考え方です。
欠勤控除については、労働基準法での定めがないため、会社で独自に定め、就業規則に規定します。
残業代のルールをそのまま適用するのも1つの考え方ですが、それにとらわれる必要はありません。仮にその月の全てを欠勤した時、残業代のルールを適用した場合、上記の手当や固定残業代(みなし残業代)は支給されます。
各手当の性質をもとに、会社としての考え方を基準に具体的に定めてください。
欠勤控除の具体的な計算方法

次に、1日当たりの欠勤控除額を求める際の基準について考えてみましょう。
残業代の計算に当たっては、月平均所定労働時間をもとに算出した1時間あたりの給与額
がベースとなります。
欠勤控除については、労働基準法に定めが無いので各社で定めます。具体的には次の計算方法があります。
1.月平均所定労働日数から計算する方法
2.その月の所定労働日数から計算する方法
3.その月の暦日数から計算する方法
この中でベストな計算方法は何かを知りたいことと思います。が、実はどれも一長一短があるので、会社の考え方としてどの方法が良いのかを決めるしかありません。
残業代の計算に当たっては、月平均所定労働時間をもとに算出した1時間あたりの給与額
がベースとなります。
欠勤控除については、労働基準法に定めが無いので各社で定めます。具体的には次の計算方法があります。
1.月平均所定労働日数から計算する方法
2.その月の所定労働日数から計算する方法
3.その月の暦日数から計算する方法
この中でベストな計算方法は何かを知りたいことと思います。が、実はどれも一長一短があるので、会社の考え方としてどの方法が良いのかを決めるしかありません。
月平均所定労働日数から計算する方法
月平均所定労働日数をもとに計算する方法が、残業代の計算に準じたものになります。
月平均所定労働日数は、年間所定労働日数【年間暦日数※-年間休日】÷12か月で算出します。※365日(閏年は366日)
例)年間休日が125日の場合、月平均労働日数は20日になります。
年間所定労働日数:365日-125日=240日
月平均所定労働日数:240日÷12か月
この計算方法を採用する場合、欠勤5日の場合は、常に欠勤控除額は次の計算になります。
5日欠勤の場合の控除額=月給÷20日×5日
月給20万円の場合、欠勤控除額は5万円となり、給与明細支給、控除には下記の記載となります。
(20万円すべてを基本給とした場合)
支給欄:基本給20万円
控除欄:欠勤5万円
この計算方法は、欠勤1日当たりの控除額が年間を通して一定になる点で分かりやすい採算方法です。一方で、所定労働日数が19日の月に全て欠勤しても、欠勤控除は19日分。1日分は支給されるという矛盾は残ります。
同じ月給20万円の場合、下記の給与明細となります。
支給欄:基本給20万円
控除欄:欠勤19万円
全て欠勤しているにもかかわらず、支給額と控除額に1万円の差があるのは疑問に感じます。
この矛盾を解消するためには、欠勤控除(減算方式)でなく日割支給(加算方式)という方法があります。出勤した日をもとに日割支給するという方法です。
日割支給(加算方式)であれば、先ほどの月平均所定労働日数が20日、その月の所定労働日数が19日で全て欠勤した場合、出勤日数がゼロなので、日割支給もゼロになります。
ところが、日割支給(加算方式)にも矛盾が生じます。19日全て出勤しても、20日分の19日にしかならないのです。
月平均所定労働日数から計算する以上は避けることができないので、割り切るしかありません。
その上で、欠勤控除と日割支給をこのように使い分けるといいでしょう。
・出勤10日までは日割支給(加算方式)
・出勤10日を超えると欠勤控除(減算方式)
月平均所定労働日数は、年間所定労働日数【年間暦日数※-年間休日】÷12か月で算出します。※365日(閏年は366日)
例)年間休日が125日の場合、月平均労働日数は20日になります。
年間所定労働日数:365日-125日=240日
月平均所定労働日数:240日÷12か月
この計算方法を採用する場合、欠勤5日の場合は、常に欠勤控除額は次の計算になります。
5日欠勤の場合の控除額=月給÷20日×5日
月給20万円の場合、欠勤控除額は5万円となり、給与明細支給、控除には下記の記載となります。
(20万円すべてを基本給とした場合)
支給欄:基本給20万円
控除欄:欠勤5万円
この計算方法は、欠勤1日当たりの控除額が年間を通して一定になる点で分かりやすい採算方法です。一方で、所定労働日数が19日の月に全て欠勤しても、欠勤控除は19日分。1日分は支給されるという矛盾は残ります。
同じ月給20万円の場合、下記の給与明細となります。
支給欄:基本給20万円
控除欄:欠勤19万円
全て欠勤しているにもかかわらず、支給額と控除額に1万円の差があるのは疑問に感じます。
この矛盾を解消するためには、欠勤控除(減算方式)でなく日割支給(加算方式)という方法があります。出勤した日をもとに日割支給するという方法です。
日割支給(加算方式)であれば、先ほどの月平均所定労働日数が20日、その月の所定労働日数が19日で全て欠勤した場合、出勤日数がゼロなので、日割支給もゼロになります。
ところが、日割支給(加算方式)にも矛盾が生じます。19日全て出勤しても、20日分の19日にしかならないのです。
月平均所定労働日数から計算する以上は避けることができないので、割り切るしかありません。
その上で、欠勤控除と日割支給をこのように使い分けるといいでしょう。
・出勤10日までは日割支給(加算方式)
・出勤10日を超えると欠勤控除(減算方式)
その月の所定労働日数から計算する方法
月平均所定労働日数から計算する方法の矛盾を解消するのが、その月の所定労働日数から計算する方法です。
例えば、月給20万円、所定労働日数19日の場合、1日当たりの欠勤控除額は15,026円になります。
20万円÷19日×1日=10526.3…
※端数処理は、労働者が有利になるよう切り捨て、切り上げをします。
欠勤控除の場合切り捨てになります。
日割計算の場合は切り上げになります。
19日全て欠勤すると、所定労働日数19日、欠勤19日になるので支給額はゼロになるので、計算はスッキリです。
一方で、所定労働日数が月に19日、20日、21日などと変動します。1日の欠勤控除額も月によって変動するという矛盾があります。
この矛盾を解消する方法、というか考え方になるのですが、そもそも毎月の所定労働日数は変動します。それに対して月給が固定給であれば、1日当たりの給与額が月によって変動するということになります。そう考えると、1日あたりの欠勤控除が変動するのもおかしくないと言えます。
例えば、月給20万円、所定労働日数19日の場合、1日当たりの欠勤控除額は15,026円になります。
20万円÷19日×1日=10526.3…
※端数処理は、労働者が有利になるよう切り捨て、切り上げをします。
欠勤控除の場合切り捨てになります。
日割計算の場合は切り上げになります。
19日全て欠勤すると、所定労働日数19日、欠勤19日になるので支給額はゼロになるので、計算はスッキリです。
一方で、所定労働日数が月に19日、20日、21日などと変動します。1日の欠勤控除額も月によって変動するという矛盾があります。
この矛盾を解消する方法、というか考え方になるのですが、そもそも毎月の所定労働日数は変動します。それに対して月給が固定給であれば、1日当たりの給与額が月によって変動するということになります。そう考えると、1日あたりの欠勤控除が変動するのもおかしくないと言えます。
その月の暦日数から計算する方法
3つめの方法は、その月の暦日数をもとに計算する方法です。
例えば、月給20万円、10月だと所定労働日数31日になるので、1日当たりの欠勤控除額は6,451円になります。
20万円÷31日×1日=6451.6…
※端数処理は、労働者が有利になるよう切り捨て、切り上げをします。
欠勤控除の場合切り捨てになります。
日割計算の場合は切り上げになります。
この方法の場合、休日も含めて1日当たりの欠勤控除額を算出するので、控除額が低くなります。また、10月の休日が9日だとすると、全て欠勤しても9日間の給与が発生します。
それに、休日というのは労働義務が無い日なので、それを日数としてカウントすること自体に違和感があります。
1つ目の月平均所定労働日数から計算する方法、2つ目のその月の所定労働日数から計算する方法のいずれかを選択するのが良いかと考えます。
例えば、月給20万円、10月だと所定労働日数31日になるので、1日当たりの欠勤控除額は6,451円になります。
20万円÷31日×1日=6451.6…
※端数処理は、労働者が有利になるよう切り捨て、切り上げをします。
欠勤控除の場合切り捨てになります。
日割計算の場合は切り上げになります。
この方法の場合、休日も含めて1日当たりの欠勤控除額を算出するので、控除額が低くなります。また、10月の休日が9日だとすると、全て欠勤しても9日間の給与が発生します。
それに、休日というのは労働義務が無い日なので、それを日数としてカウントすること自体に違和感があります。
1つ目の月平均所定労働日数から計算する方法、2つ目のその月の所定労働日数から計算する方法のいずれかを選択するのが良いかと考えます。
遅刻や早退の控除について

ここまでは欠勤控除についての解説をしました。
では、遅刻や早退の場合の計算方法はどうなるのでしょうか?
特に遅刻3回につき1日欠勤とみなすという話をよく耳にしますが、同じようなルールを作っても良いのでしょうか?
あるいは、遅刻の理由が公共交通機関の延着によるものであった場合、遅刻控除をしてはいけないのでしょうか?これらについて解説いたします。
では、遅刻や早退の場合の計算方法はどうなるのでしょうか?
特に遅刻3回につき1日欠勤とみなすという話をよく耳にしますが、同じようなルールを作っても良いのでしょうか?
あるいは、遅刻の理由が公共交通機関の延着によるものであった場合、遅刻控除をしてはいけないのでしょうか?これらについて解説いたします。
遅刻や早退:具体的な控除方法
遅刻や早退に関する控除も、基本的には欠勤控除の計算方法を同じです。
欠勤控除は1日を単位とするのに対し、遅刻や早退控除は時間を単位にします。
欠勤控除の計算方法を、月平均所定労働日数をもとに計算する場合は、月平均所定労働時間を算出します。
欠勤控除の計算方法を、その月の所定労働日数をもとに計算する場合は、その月の所定労働時間を算出します。
欠勤控除は1日を単位とするのに対し、遅刻や早退控除は時間を単位にします。
欠勤控除の計算方法を、月平均所定労働日数をもとに計算する場合は、月平均所定労働時間を算出します。
欠勤控除の計算方法を、その月の所定労働日数をもとに計算する場合は、その月の所定労働時間を算出します。
遅刻3回で1日欠勤とみなすはOKか?
ここまで解説してきましたのは、あくまでノーワーク・ノーペイの原則によるもの。欠勤や遅刻・早退は、その時間分仕事をしていないので控除しますといういわば当たり前のこと。
一方で、遅刻をするのはけしからん!ということで、同じ月に複数回重ねると欠勤1日とみなし給料から控除するという話をよく耳にします。
結論から申しますと、この方法はお薦めできません。
その理由は2つあります。
1.ノーワークを超える控除は懲戒の減給処分にあたる
1つ目は、遅刻や早退の時間に対する控除は問題ありません。ですが、働いている時間に対しては全額給与を支払う必要があります。それを一部控除するのは懲戒の減給処分にあたります。懲戒処分にするには、就業規則に規定されているかという問題があります。規定されていたとしても、懲戒権の乱用に当たらないかという問題があります。遅刻3回に至るまで、どのような指導をしてきたのか、あるいはその遅刻の持つ意味合いの重さ等にもよりますが、単に3回遅刻というのは疑問が残ります。
2.減給額の上限を超えないか
2つ目は、その減給処分が適切なものであったとしても、減給額の上限を超えない範囲でなければなりません。
減給額の上限は以下のように定められています。
① 減給1回当たり平均賃金の1日分の半額
② 一賃金支払期当たり、賃金総額の10分の1
遅刻3回で欠勤1日とみなす場合、②の一賃金支払期当たり賃金総額の10分の1には収まりますが、①の減給1回当たり平均賃金の1日分の半額を超えることになります。
それ以上に、減給という制裁金を払うことで罪悪感を帳消しにするという心理も働くと言われています。遅刻による減給を規定することは必要です。
ですが、実効性を上げるという意味では、まずは指導・教育からスタートし、その後は第一段階の戒告処分から徐々に上げていくことをお薦めします。
一方で、遅刻をするのはけしからん!ということで、同じ月に複数回重ねると欠勤1日とみなし給料から控除するという話をよく耳にします。
結論から申しますと、この方法はお薦めできません。
その理由は2つあります。
1.ノーワークを超える控除は懲戒の減給処分にあたる
1つ目は、遅刻や早退の時間に対する控除は問題ありません。ですが、働いている時間に対しては全額給与を支払う必要があります。それを一部控除するのは懲戒の減給処分にあたります。懲戒処分にするには、就業規則に規定されているかという問題があります。規定されていたとしても、懲戒権の乱用に当たらないかという問題があります。遅刻3回に至るまで、どのような指導をしてきたのか、あるいはその遅刻の持つ意味合いの重さ等にもよりますが、単に3回遅刻というのは疑問が残ります。
2.減給額の上限を超えないか
2つ目は、その減給処分が適切なものであったとしても、減給額の上限を超えない範囲でなければなりません。
減給額の上限は以下のように定められています。
① 減給1回当たり平均賃金の1日分の半額
② 一賃金支払期当たり、賃金総額の10分の1
遅刻3回で欠勤1日とみなす場合、②の一賃金支払期当たり賃金総額の10分の1には収まりますが、①の減給1回当たり平均賃金の1日分の半額を超えることになります。
それ以上に、減給という制裁金を払うことで罪悪感を帳消しにするという心理も働くと言われています。遅刻による減給を規定することは必要です。
ですが、実効性を上げるという意味では、まずは指導・教育からスタートし、その後は第一段階の戒告処分から徐々に上げていくことをお薦めします。
公共交通機関の延着による遅刻は給料から控除できない?
遅刻には公共交通機関の延着によるものもあります。その際、ほとんどの会社ではやむを得ない理由として、給料から控除しないとしています。
では、この場合給料から遅刻した分を控除することはできないのでしょうか?
確かにいつも乗っている電車が遅れると、遅刻するのも不可抗力と言えます。それをもって遅刻をしたという勤怠としての評価を下すのは適切でないかもしれません。ですが、それと給与からの控除とは全く話が違います。
ノーワーク・ノーペイですので、その時間分を給料から控除するのは全く問題がありません。
延着といっても10分程度であれば、遅刻する始業時刻ギリギリにタイムカードを押す人。
少し余裕を持って出勤している人なら遅刻にならないでしょう。同等に扱っていいのかという疑問もあります。
必要以上に早く出勤する方向に誘導することになっては本末転倒ですが、このようなところに会社の考え方を表現することもできます。
では、この場合給料から遅刻した分を控除することはできないのでしょうか?
確かにいつも乗っている電車が遅れると、遅刻するのも不可抗力と言えます。それをもって遅刻をしたという勤怠としての評価を下すのは適切でないかもしれません。ですが、それと給与からの控除とは全く話が違います。
ノーワーク・ノーペイですので、その時間分を給料から控除するのは全く問題がありません。
延着といっても10分程度であれば、遅刻する始業時刻ギリギリにタイムカードを押す人。
少し余裕を持って出勤している人なら遅刻にならないでしょう。同等に扱っていいのかという疑問もあります。
必要以上に早く出勤する方向に誘導することになっては本末転倒ですが、このようなところに会社の考え方を表現することもできます。
まとめ
欠勤控除は企業の経済的健全性を維持するだけでなく、従業員のモチベーションや業績にも大きく影響します。公平かつ透明性を持って取り組むことが、長期的な企業の成長と従業員の満足度向上の鍵となります。この記事を通じて、欠勤控除の基礎理解を深め、その適切な運用方法についてのヒントを得ることができたことを願っています。正確な知識と実践的なアプローチで、欠勤控除を企業の強みとして活用しましょう。
当社労士事務所は大阪、堺市、を中心に様々な企業の問題に取り組んでおります。
【関連記事はこちら】
当社労士事務所は大阪、堺市、を中心に様々な企業の問題に取り組んでおります。
【関連記事はこちら】